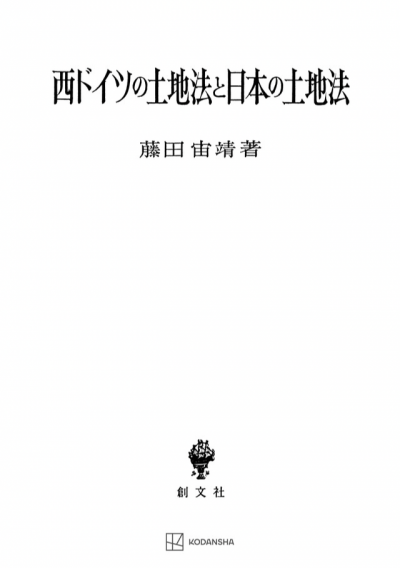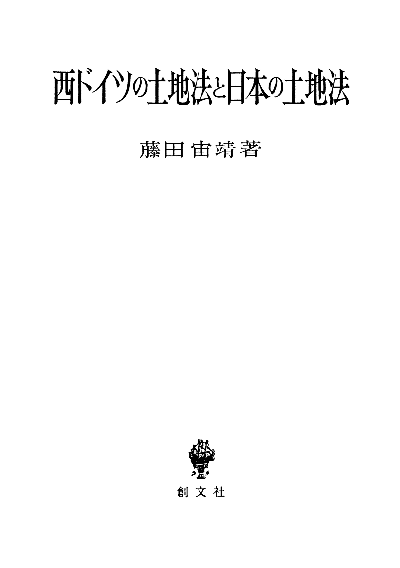西ドイツの土地法と日本の土地法
西ドイツの土地法と日本の土地法
本商品は「旧ISBN:9784423730416」を底本にしたオンデマンド版商品です。
初刷出版年月:1988年
確固たる体系を持つ西ドイツ土地法を手がかりに、わが国現行土地法(公法)の持つ特徴と問題点を剔抉し、その克服の道を明示する。
【目次より】
はしがき
第一部 建築の自由と土地利用規制 西ドイツ法の場合
I 建築の自由と土地利用規制
一 はじめに
二 西ドイツの建築規制法制
三 我国の場合
四 西ドイツ土地利用規制法制の法思想的基盤
五 むすび
II 西ドイツの国土整備計画法制
都市的土地利用と農村的土地利用との調整を中心として
一 はじめに
二 建築規制法制の基本的構造
三 市町村の建設管理計画(Bauleitplane)による
都市的土地利用と農村的土地利用の調整
四 上位計画とその意義
五 むすび
III プロイセンの住宅地新開発規制立法(Ansiedlungsgesetzgebung)
について 西ドイツ都市建設法制におけるssssenbereichの概念とその沿革
一 はじめに 問題の所在
二 西ドイツ現行建設法典上のAussenbereichの概念と
一九三六年建築規制令(BebauVO)におけるその先行形態
三 プロイセン住宅地新開発規制法制(Ansiedlungsgesetzgebung)
四 むすび
IV 財産権の保障とその限界
ボン基本法下三〇年の西ドイツ公法学におけるその一断面
一 はじめに
二 ボン基本法の "Eigentumsverfassung" と土地所有権の
社会的拘束(Soziabindung)
三 むすび
第二部 土地と財産権保障 日本法の場合
I 日本国憲法と財産権保障 土地所有権を中心として
一 はじめに
二 憲法上の財産権保障とその限界
三 近代的財産権保障制度の修正
四 損失補償制度
II 公共用地の強制的取得と現代公法 関連諸利益の取扱い方を中心として
一 はじめに
二 公共用地の強制的取得と「私益」
三 公共用地の強制的取得と「公益」
四 むすび
III 残地補償と起業利益ならびに事業損失との関係について
一 はじめに
二 残地に生じた起業利益の取扱い方 土地収用法九〇条の射程距離
三 事業損失と残地補償 四 むすび
IV 公共用地の任意買収と土地収用との相互関係について
一 はじめに
二 具体的な問題例 その一
三 具体的な問題例 その二
四 問題解決への手掛り
五 問題解決への試み
六 むすび
V 土地区画整理制度と財産権保障 いわゆる「無償減歩」をめぐって
一 はじめに
二 問題の所在について
三 西ドイツの場合(一)
四 西ドイツの場合(二)
五 むすび
VI 土地所有権の制限と損失補償
一 はじめに
二 土地所有権の保障についての「決定理論」と「オープン理論」
三 我国裁判例の動向
四 都市計画上の権利制限と損失補償
五 むすび
VII 我国地区計画制度の性格
西ドイツ地区詳細計画(Bプラン)制度との対比におけるその特色と問題点
一 はじめに
二 地区計画制度と「建築の自由」
三 地区計画と公共性 計画実現に向けての行政主体の責任と負担
四 むすび
VIII 不動産取引の公法的規制 土地売買の認可制度を中心として
一 はじめに
二 基本的視角
三 我国の法制の特徴
四 むすび
■
著者
藤田 宙靖(フジタ トキヤス)
1940年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。元最高裁判所判事。 東京大学法学部卒業。法学博士(東京大学)。専門は、行政法。
法学博士(東京大学)。
著書に、『公権力の行使と私的権利主張』『西ドイツの土地法と日本の土地法』『行政法学の思考形式(増補版)』『行政法の基礎理論(上・下巻)』『行政組織法』『現代法律学講座 行政法1総論(第4版改訂)』『最高裁回想録 学者判事の七年半』『行政法入門(第6版)』『新版 行政法総論』などがある。
受取状況を読み込めませんでした