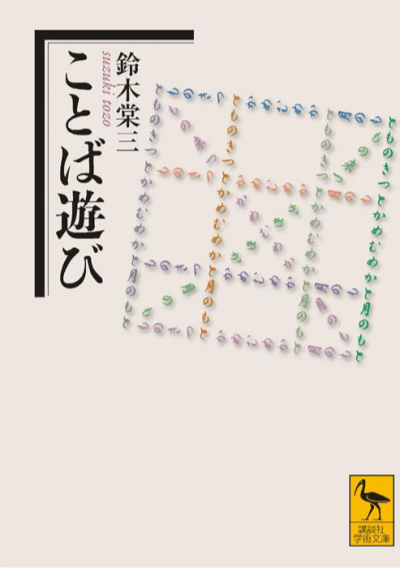ことば遊び
ことば遊び
◆重要◆
【表紙のデザインについて】
・この本の表紙は、
商品画像2枚目にあるサンプルと同様の
統一フォーマットになります。
【内容紹介】
「世の中はすむと濁るの違いにて、刷{は}毛{け}に毛があり禿に毛が無し」。平安以来、歌詠みも、連歌作者も、俳諧の宗匠も、ことばの動き、その変わり身の様々な相を追求した。「回文」「早口ことば」「しゃれ」「地口」「なぞ」「解きと心」……。
百花繚乱の言語遊戯を誇る日本語。ことばの可能性を極限まで発掘しようとする行為としてのことば遊びの歴史を辿る。
「ことばの機能の眠っている部分を揺り起こし、潜在していた変化の万華相と、その面白さ美しさを見付け出したという実績が、ことば遊びの歴史にはある(中略)しゃれを愛するのは、日本人の国民性であるといってよい。(中略)しゃれのわからぬ日本人は、ユーモアを解しないというだけでなく、風流の嗜{たしな}みに欠ける人間と考えられた。」(本文より抜粋)
*1975年に中央公論社から刊行された同名の書を文庫化したものです。当文庫への収録にあたり、著作権継承者の諒解を得て明らかな誤植等について訂正を加えました。
【目次】
第一章 ことば遊びの世界
はじめに
ことばとことば遊び 宗祇の挿話 清みと濁りの違い 鸚鵡返し 逆さ読みいろは
尻取りことば
口拍子のよい尻取り 尻取童唄 文字鎖
回 文
回文の規則 回文歌 回文俳諧 回文の連句集 八重襷
第二章 早口ことば
早物語の系譜
早 歌 てんぽ物語 口遊び
ういろう売のせりふ
ういろう由来 団十郎の創出 舌もじり・早口文句の集成 一九のせりふ こんきょうじの歌詞
舌もじりの練習
名調子のういろう売 明治時代の舌もじり アナウンスの訓練
第三章 しゃれ
しゃれの語系
興言・利口 洒落としゃれ シャレル・ジャレル
秀句・こせごと・かすり
秀句の意味転化 こせごと かすりの多面性
口 合
しゃれとしての口合 『穿当珍話』 口合の心得書 絵口合
地 口
地口諸説 地口付 『地口須天宝』 地口行灯
もじり・語路
字もじり・本もじり 語路・語呂合
無理問答
無理問答の約束 無理問答の祖型 無理問答本
第四章 な ぞ
古代のなぞ
中国のなぞ 字 謎 一伏三向、三伏一向 ワザウタ
なぞなぞ合
なぞなぞ物語 『枕草子』の挿話 小野宮家歌合 平安のなぞの技法
なぞの型
『徒然草』のなぞ なぞの解 複数解の出るなぞ 連歌の賦物 賦物型のなぞ 観察型のなぞ
なぞの本
『宣胤卿記』 『見聞雑記』 『なぞだて』 『謎 立』 『酔醒記』 『あたうがたり』 『謎乃本』 『寒川入道筆記』
解きと心
三段なぞの胎動 享保期の三段なぞ はじめにしゃれありき 題材の新しさ 頓智謎興行 寄席のなぞ解き
判じ物
長い伝統 「今朝ほどの」 『なぞなぞ集』 隠 句
伝承のなぞ
失われたなぞ 子供のなぞ 口拍子調のなぞなぞ 大人から子供へ 民俗なぞと文芸 定まり文句 納戸の懸金 新しいなぞ
原本あとがき
■
著者
鈴木棠三(すずき・とうぞう)
1911年、静岡県生まれ。国学院大学国文科卒業。同大学研究科修了。元・白梅学園短期大学教授。専攻は国文学、民俗学、口承文芸。1992年没
受取状況を読み込めませんでした