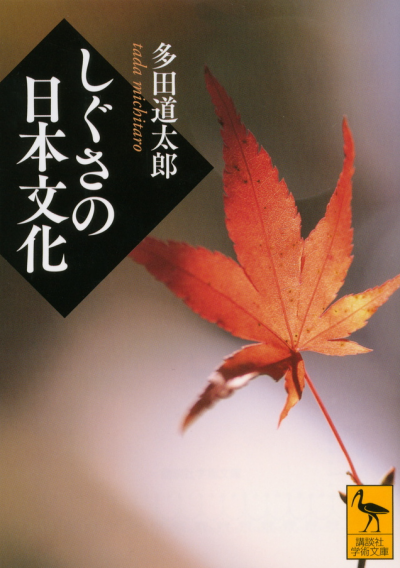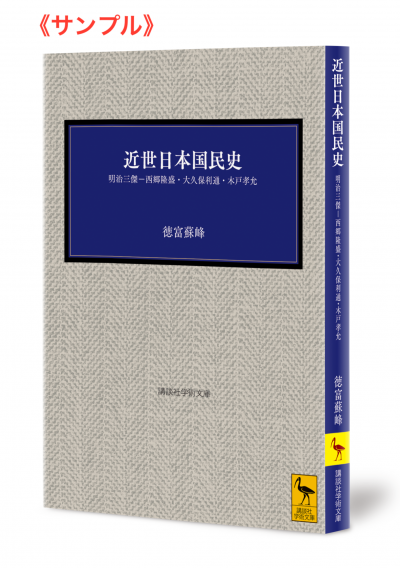しぐさの日本文化
しぐさの日本文化
◆重要◆
【表紙のデザインについて】
・この本の表紙は、
商品画像2枚目にあるサンプルと同様の
統一フォーマットになります。
【内容紹介】
日常の出来事や風俗から日本文化をとらえる評論で知られる著者の真骨頂ともいえるエッセイ集。「ものまね」の芸に惹かれる心性、「しゃがむ」姿勢と文明との関係、指などによる身振り語ともいえるような身体化されたかたちや動作など、日本的なしぐさ、ことに「低さ」に通じるしぐさの数々から、深い意味を洞察する。(講談社学術文庫)
日常の出来事や風俗から日本文化をとらえる評論で知られる著者の真骨頂ともいえるエッセイ集。「ものまね」の芸に惹かれる心性、「しゃがむ」姿勢と文明との関係、指などによる身振り語ともいえるような身体化されたかたちや動作など、日本的なしぐさ、ことに「低さ」に通じるしぐさの数々から、深い意味を洞察する。
【目次】
ものまね I
ものまね II
ものまね III
頑張る
あいづち
へだたり
低姿勢
寝ころぶ
握手
触れる
にらめっこ
はにかみ
笑い
微笑
作法 I
作法 II
いけばな
つながり
かたち
坐る I
坐る II
しゃがむ I
しゃがむ II
なじむ
七癖 I
七癖 II
腕・手・指
指切り
すり足 I
すり足 II
すり足 III
あてぶり
見たて I
見たて II
直立不動
表情
咳払い I
咳払い II
くしゃみ
あくび
泣く I
泣く II
むすぶ
解説対談 純粋溶解動物──加藤典洋と
■
著者
多田 道太郎(ただ・みちたろう)
1924(大正13)年京都に生まれる。フランス文学者、評論家。京都大学文学部卒。京都大学名誉教授。退官後は明治学院大学、武庫川女子大学などで教鞭をとった。ルソーやボードレールの研究のほか、日常の出来事や風俗から日本文化をとらえる評論で知られる。1999年「変身放火論」で伊藤整文学賞。2007年没
受取状況を読み込めませんでした