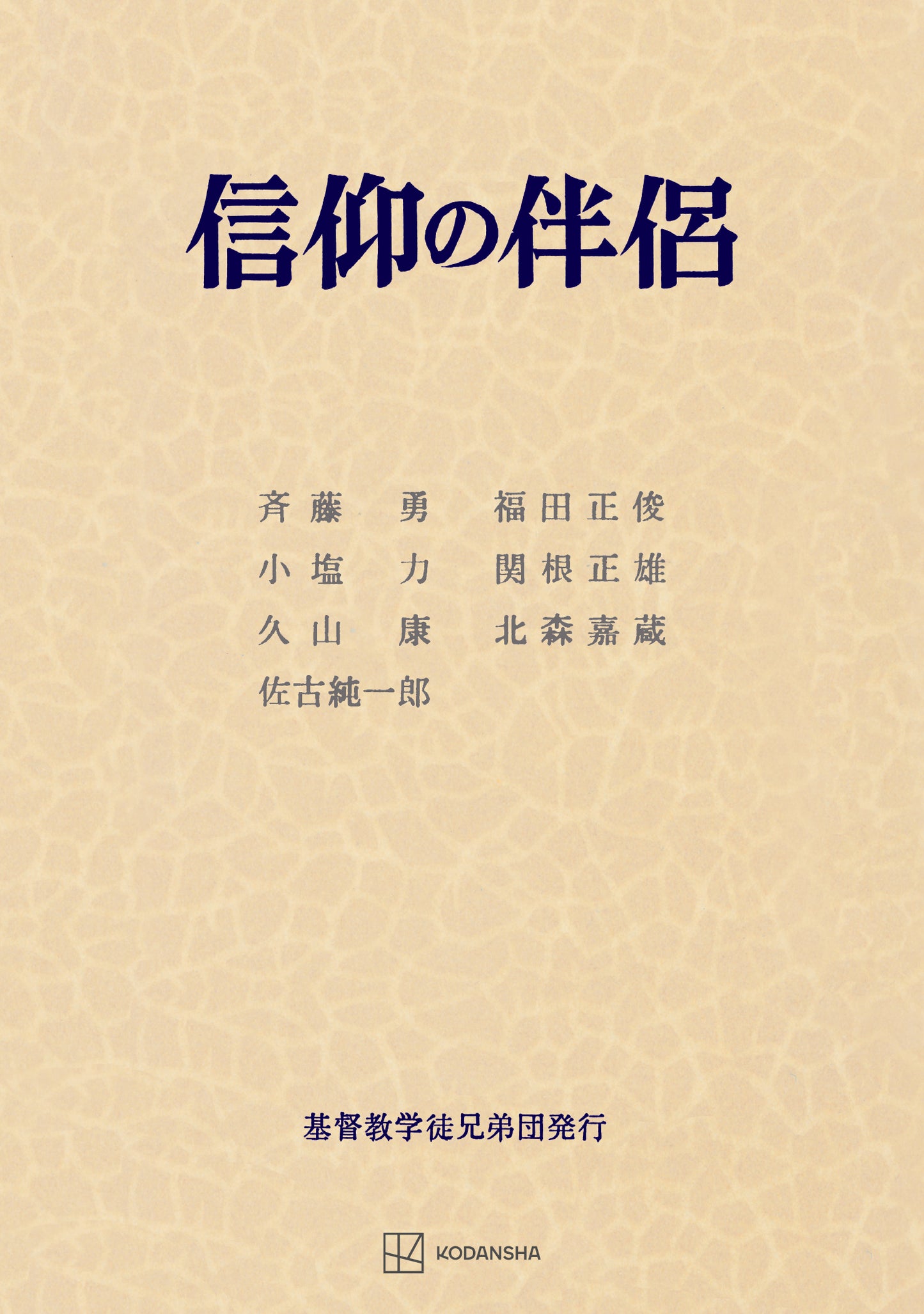信仰の伴侶
信仰の伴侶
ドストエフスキーはかつて、自分は現代の産物であり、したがって無信仰と懐疑の子だ、しかしそれゆえにまた信仰への渇望に苦しめられると告白した。
この書は転換期の激浪のなかで、この世的なるものに寄る辺を失いつつある魂に対しての最後の希望となる信仰を考えるために書かれた。
哲学者、神学者、文芸評論家が、「信仰」と「魂」について、さまざまな光をあてる。
【目次】
第一部 信仰への道
明治時代における信仰への遍歴
明治の青春としてのキリスト教
西洋文化の代表としてのキリスト教の受容
私の學生時代 齋藤勇氏
高山樗牛・徳富蘆花・綱島梁川
スピノザ「エテイカ」、トルストイ「懺悔」
植村正久
島崎藤村と有島武郎
日本文學とキリスト教
明治の文學者のキリスト教離脱への反省
芥川龍之介及び太宰治とキリスト教
椎名麟三の受洗
【略】
キリスト教的世界よりギリシャ的世界へ
聖書の世界への還帰
晩年の内村鑑三
信仰への巡禮 佐古純一郎氏
死の不安
「歎異抄」
一燈園
太宰治への傾倒
田邊元「歴史的現実」と応召
新約聖書
椎名麟三とドストイエフスキイの影響
小林秀雄のドストイエフスキイ研究
椎名麟三とキリスト教
第二部 信仰書の勧め
高倉徳太郎の著作
パスカルに関する書物
【略】
アンセルムスとエックハルト
ドストイエフスキイとキェルケゴール
バルト、カルヴィン、ルター、フォーアサイス
内村鑑三
【略】
説教集と辭典
戰後の諸作
イエス伝
イエス伝の歴史的変遷
第三部 聖書の読み方
聖書の読み方
一般的な読書と異る聖書の読み方/聖書を読むときの態度/
青年のもつ宗教性/聖書による人生觀の変化/ヒューマニズムの高揚と破壊/
聖書の読み方の常道/青年の読み方と老人の読み方【略】
興味を覚えた聖書の箇所 齋藤氏
聖書の飜訳について
私の聖書への接し方 佐古氏、小塩氏
詩人と教授/キェルケゴールの父の聖書の教え方
私の聖書への接し方 関根氏
どこから聖書を読むべきか/ルカ伝とロマ書/福音書の特色/
使徒行伝の意義/使徒の書翰の意義/ペテロ書翰とパウロ書翰/默示録【略】
■
著,編
久山 康(くやま やすし)
1915〜1994年。哲学者、宗教学者。関西学院大学元院長、同名誉教授。京都帝国大学文学部哲学科卒。
著書に、『自然と人生』『現代人と宗教』『近代日本の文学と宗教』『落暉にむかいて』『文学における生と死』『四季折りおりの歌 現代の秀句・秀歌の鑑賞』『人間を見る経験』『ヨーロッパ心の旅』『人に会う自己に会う』など、
訳書に、キェルケゴール『愛は多くの罪を掩ふ』キエルケゴール『野の百合・空の鳥』『キエルケゴールの日記』などがある。
受取状況を読み込めませんでした