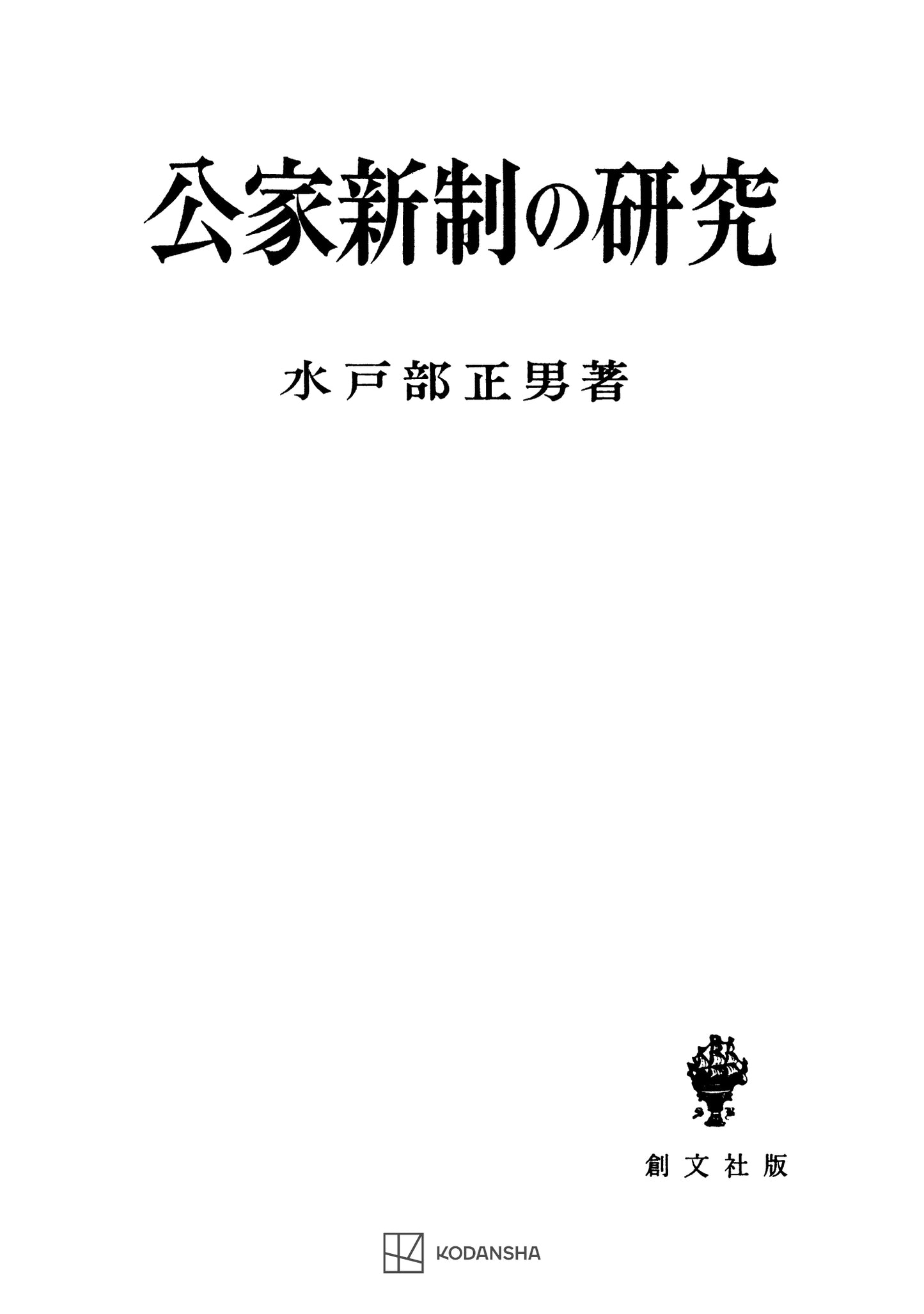公家新制の研究
公家新制の研究
「公家新制」は、平安中期から南北朝時代にかけて天皇・上皇の勅旨に基づいて制定された成文法典の呼称である。別名、制符(せいふ)ともされる。最古の新制は、947年に村上天皇が出した新制6ヶ条と呼ばれている。長保元年(999年)に一条天皇・藤原道長体制下で出された長保元年令11条は、後の新制の定形となった。「公家新制」の変遷に時代の変化を読み取る。
【目次】
序文
序章
はしがき
一 公家新制とは何か
二 平安・鎌倉時代の公家新制一覧表
第一章 公家新制の成立 天暦一・一一・一三新制
第二章 平安時代の公家新制
一 天延三年及び天元五年の新制
(一)天延三年新制の史料
(二)天元五年新制の史料
二 一条天皇と新制
(一)永延一・三・五新制
(二)永延一・三・七新制か
(三)永延一・五・五新制
(四)永延二・四・一四新制
(五)正暦年代の新制
(イ)正暦一・四・一新制
(ロ)正暦符
(六)長保年代の新制
(イ)長保一・七・二七新制
(ロ)長保二・六・五新制
(ハ)長保三・壬一二・八新制
三 長和二・四・一九新制
四 白河・鳥羽両院時代の新制
(一)永久四・七・一二新制
(二)庄園整理令
第三章 後白河上皇時代の公家新制
一 保元・治承の新制と建久の新制との関係
(一)保元一・壬九・一八新制(保元一年令と略称)
(二)保元二・一〇・八 新制(保元二年令と略称)
(三)治承二・壬六・一七新制
(四)治承二・七・一八新制
(五)治承三・八・三〇新制
(六)建久年代の新制と鎌倉時代の新制の関係
二 保元・治承年代の新制各説
(一)保元一年令
(二)保元二年令
(三)治承二・七・一八令
三 建久二・三・二二新制(建久I令と略称)
四 建久二・三・二八新制(建久II令と略称)
付録 興福寺の寺辺新制
第四章 鎌倉時代の公家新制
一 建暦二・三・二二新制
付録 「けちうのしんせい」
二 嘉禄一・一〇・二九新制
三 寛喜三・一一・三新制
四 延応二・三・一二新制
五 建長五・七・一二新制
六 弘長三・八・一三新制
七 文永一〇・九・二七新制
八 正応五・七・?新制
第五章 公家新制と武家新制の関係
一 鎌倉幕府施行の新制一覧表
二 延応二年の関東新制
三 弘長一年の関東新制
四 結び
索引
■
著者
水戸部 正男(みとべ まさお)
1912〜1996年。日本史学者。元横浜国立大学学長。東京文理科大学国史学科卒業。専門は日本の法制史。
著書に、『公家新制の研究』『日本史概説史料』『日本史上の天皇』『後醍醐天皇』『ラバウル戦友記 南海派遣第十四野戦郵便隊の記録』『図説 歴代天皇紀』(共著)などがある。
受取状況を読み込めませんでした