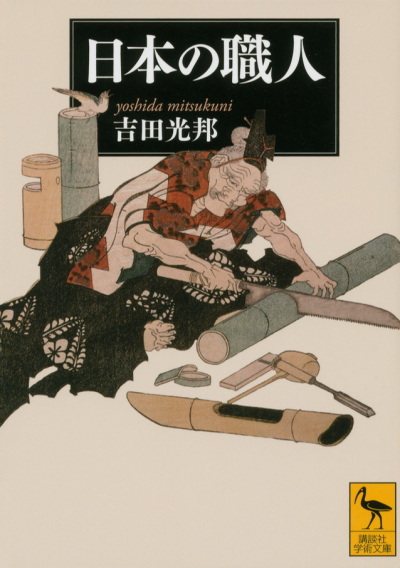日本の職人
日本の職人
◆重要◆
【表紙のデザインについて】
・この本の表紙は、
商品画像2枚目にあるサンプルと同様の
統一フォーマットになります。
【内容紹介】
青銅鏡、墨、刺繍、タタラ製鉄、漆、べっ甲細工、扇、鯉のぼり、蒔絵(まきえ)、焼き物、竹細工……。二十世紀後半、科学技術史家である著者は、職人の仕事場を訪ね歩き、伝統の技とその現状を報告する。現代へとつながる、中世〜近代の日本における職人の変遷を概観し、苦しくも誇り高き手仕事を再評価する。職人の盛衰から日本文化を読み解く試みでもある。この風土の繊細で闊達な手仕事の魅力を探る!現場ルポと歴史の両面から、伝統技術と日本文化を問い直す。
「とりちらされた竹屑の間には、とぎすまされてつめたく鋼鉄の肌を光らせる刃物が見える。……さまざまな形をした工具もある。そのどれもが長い間の手ずれで光っている。それらの形ひとつにも職人たちの独自の考案と工夫のあとがある。……それをまるで自分の手足のように自由自在に取り扱って、……物をつくり出す。そのひとつひとつに彼らの人間的なエネルギーがじっくりと注ぎこまれる。……すべてに充ちているのはほのかな温かさである。こうした生産活動をつづける人たち、それが職人である。日本の職人たちである。」(「プロローグ」より)
※本書の原本は、1976年に角川書店より刊行されました。
【目次】
プロローグ 京の扇
第一部 現代の職人── 一九五〇年代
第一章 京の職人
青銅の鏡/京の鏡師/日本の扇/鏡と扇/ある仏師/仏像のつくり方
第二章 金沢の職人
加賀象嵌/ある刺繍師/蒔絵師の話
第三章 忘れられた職人
タタラの職人/最後のタタラ職人
第四章 漆の仕事
漆の運命/輪島の塗師/会津の塗師/カシューの塗装
第五章 やきものの世界
丹波のやきもの/機械と道具/薩摩のやきもの/京のやきもの/量産のやきもの
第二部 現代の職人── 一九七〇年代
第一章 工業社会のなかに
技術革新時代に蘇える手仕事/脱皮・変貌する職人たち/伝統技術者育成の問題点/伝統産業の方向
第二章 墨──奈良
第三章 漆塗り──輪島
第四章 たんす──岩谷堂
第五章 鯉のぼり──加須
第六章 そうめん──揖保
第七章 竹細工──大分
第八章 傘とちょうちん──岐阜
第九章 べっ甲細工──長崎
第十章 藍染──出雲
第十一章 鬼瓦──菊間
第十二章 琴──伊丹
第三部 歴史の流れ
第一章 中世の職人
歌合の職人/屏風絵の職人
第二章 江戸時代の職人
四民の制度/職人社会/徒弟制度/職人気質
第三章 明治の職人
職人社会の変革/職人から芸術家へ/職人から経営者へ/清水喜助の進出
エピローグ ふたたび現代で
職人を取り巻く誤解と錯覚/伝統的な手仕事の新しい位置づけ
付 喜多院職人尽屏風絵解
■
著者
吉田光邦(よしだ・みつくに)
1921〜1991年。京都大学理学部卒業。京都大学人文科学研究所教授、所長を歴任。京都大学名誉教授。専門は、科学技術史。
受取状況を読み込めませんでした