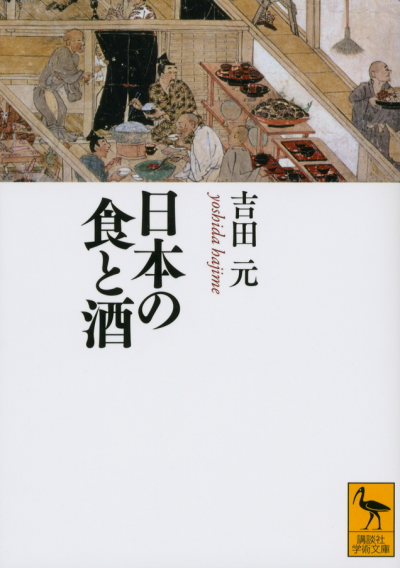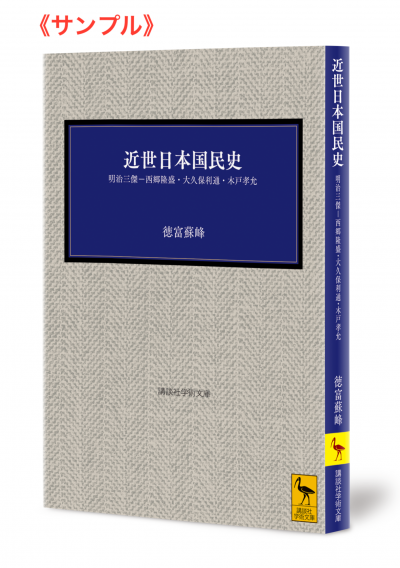日本の食と酒
日本の食と酒
◆重要◆
【表紙のデザインについて】
・この本の表紙は、
商品画像2枚目にあるサンプルと同様の
統一フォーマットになります。
【内容紹介】
日本人は何を食べていたのか。本書は京都・山科家の日記や奈良・興福寺の文書をひもとくことで、中世の公家と僧侶の食生活を再現し、その背景をなす製法の歴史へと接近する。中世から近世にかけて日本酒としてのかたちを整えていく酒。醤(醤油)、味噌、納豆といった大豆発酵食品……。日本の食文化を最も特徴付ける発酵技術と発酵文化の歴史を追い、その原点に迫る。これが日本食の原型だ!
*1991年9月に人文書院より刊行。(第1章—第3章および第5章は書き下ろし、その他収録作品参照)
【目次】
第一章 中世末の食物売りたち
歌合/狂言/供御人と食物
第二章 一五世紀公卿の食生活──『教言卿記』『山科家礼記』『言国卿記』
名字の地・山科/教言の晩年/応仁の乱/若き日の言国/供御人たち/惨劇/鞍馬参詣/食物の分類、貯蔵、調理法
第三章 一六世紀公卿の食生活──『言継卿記』『言経卿記』
『言継卿記』/言継の食生活/尾張下向/大洪水/子供たちの病気/駿府下向/東寺五重塔の焼失/信長の上洛と岐阜下向/『言経卿記』と言継の死/本能寺の変/京都追放/再び京都へ/東寺五重塔の再建/京都大地震/勅免/言経の食生活/『雍州府誌』と京都の食物
第四章 奈良興福寺の食生活──『多聞院日記』
はじめに/食物の種類/天災と飢饉/多聞院の献立/料理の内容とその他の食品/肉食・悪食
第五章 中世酒から近世酒へ
日本酒の製造法/京都の酒/僧坊酒/田舎酒とその他の酒
第六章 火入れの発展
はじめに/日本における火入れの成立//火入れの温度について/東アジア諸国における加熱殺菌法/日本の火入れの限界
第七章大豆発酵食品
醤油と味噌の製造法/室町時代以後の大豆発酵食品/多聞院の大豆発酵食品/『料理物語』の醤油/ケンペル、ツュンベリーの見た醤油/『和漢三才図会』の大豆発酵食品/酢
あとがき
文庫版あとがき
参考文献
索引
■
著者
吉田 元(よしだ はじめ)
【略歴】
1947年、京都市生まれ。京都大学農学部水産学科卒業、京都大学大学院農学研究科農芸化学専攻博士課程修了。農学博士。専門は発酵醸造学、食文化史。種智院大学教授を経て、2013年に退職し、同大学名誉教授。
【著書】
『中世の光景』(共著)朝日選書、1994年。
『童蒙酒造記・寒元造様極意伝』(翻刻・現代語訳) 日本農書全書51、農文協、1996年。
『江戸の酒』朝日選書、1997年。
『近代日本の酒づくり——美酒探求の技術史』岩波書店、2013年。
受取状況を読み込めませんでした