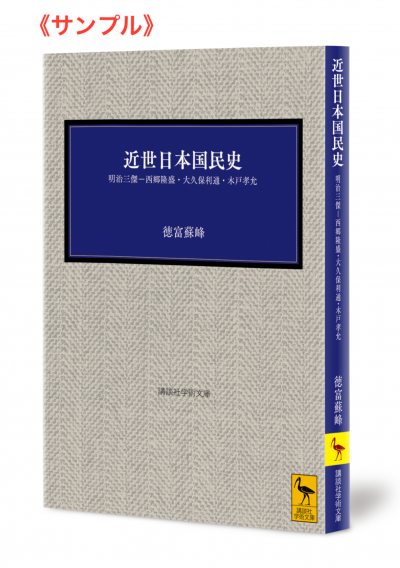永遠の平和のために
永遠の平和のために
◆重要◆
【表紙のデザインについて】
・この本の表紙は、
商品画像2枚目にあるサンプルと同様の
統一フォーマットになります。
【内容紹介】
イマヌエル・カント(1724-1804年)が1795年に発表したこの小著の日本語訳の主なものは四種類あります(高坂正顕訳(1949年)、宇都宮芳明訳(1985年)、中山元訳(2006年)、池内紀訳(2007年))。それらはすべて『永遠平和のために』というタイトルで出され、多くの読者の手にされてきました。
では、なぜあえて新しい訳を出すのか——練達の訳者は、思案した末、やはり新しい日本語訳が必要だという結論に達して、本書を仕上げました。その一例は、本書第1章のはじめにある「Friede, der das Ende aller Hostilitaten〔原文はaにウムラウト〕bedeutet」という個所です。既存の訳の訳文を一覧にすると次のようになります。
(高坂正顕訳)「平和とはあらゆる敵意の終末を意味し」
(宇都宮芳明訳)「平和とは一切の敵意が終わることで」
(池内紀訳)「平和というのは、すべての敵意が終わった状態をさしており」
(中山元訳)「平和とはすべての敵意をなくすことであるから」
これらの日本語を読むと、カントは誰もが「敵意」を捨て、心のきれいなよい人になった状態を「平和」と呼んでいる、と思うのではないでしょうか? そのとおりだとすれば、ほんの少しでも「敵意」を抱くことがあるなら、決して「平和」は訪れない、ということになります。しかし、そもそも「敵意」をまったく抱かないなどということがありうるのだろうかと考えると、カントは現実離れした理想を語っていたと感じられてきます。
でも、ここでちょっと考えてみよう、と本書の訳者は言います。原文にある「Hostilitaten」を「敵意」と訳すのは本当に正しいのだろうか、と。確かに「Hostilitat」(単数)は「敵意」だけれど、カントがここで書いているのは「Hostilitaten」という複数形です。これは「敵対行為、戦闘行為」を意味します。だから、この個所は次のように訳すべきでしょう。
(本書)「平和とは、あらゆる戦闘行為が終了していることであり」
上の四種の訳文とはずいぶん意味が異なるのではないでしょうか。こんなふうに、この著作は現実離れした理想を語ったものではなく、現実から離れずに「永遠の平和」というプロジェクトを提示したものなのです。カントの本当の意図は、本書を通してこそ明らかになるでしょう。
【目次】
第1章 国どうしが永遠の平和を保つための予備条項
その1 将来の戦争の種をひそかに留保して結んだ平和条約は、平和条約とみなすべきではない
その2 独立している国は(国の大小に関係なく)、相続・交換・売買・贈与によって別の国に取得されてはならない
その3 常備軍は、いずれ全廃するべきである
その4 対外紛争のために国債を発行するべきではない
その5 どのような国も、他国の体制や統治に暴力で干渉するべきではない
その6 どのような国も、他国との戦争では、将来の平時においてお互いの信頼を不可能にしてしまうような敵対行為をするべきではない。たとえば、暗殺者や毒殺者を雇う、降伏させない、敵国での反逆をそそのかす、などのことはするべきではない
第2章 国と国のあいだで永遠の平和を保つための確定条項
永遠の平和のための確定条項 その1 どの国でも市民の体制は共和的であるべきだ
永遠の平和のための確定条項 その2 国際法は、自由な国と国の連邦主義を土台にするべきである
永遠の平和のための確定条項 その3 世界市民の権利は、誰に対してももてなしの心をもつという条件に限定されるべきだ
補足 その1 永遠の平和を保証することについて
補足 その2 永遠の平和のための秘密条項
付 録
I 永遠の平和を考えるときの、モラルと政治の不一致について
II 公法の先験的な概念から見た、政治とモラルの一致について
■
著者
イマヌエル・カント
1724-1804年。ドイツの哲学者。主な著書に、本書(1795年)のほか、『純粋理性批判』(1781年)、『実践理性批判』(1788年)、『判断力批判』(1790年)ほか。
訳者
丘沢静也(おかざわ・しずや)
1947年生まれ。ドイツ文学者。首都大学東京名誉教授。著書に『マンネリズムのすすめ』、『下り坂では後ろ向きに』ほか。訳書に、マルクス『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(講談社学術文庫)のほか、ヴィトゲンシュタイン、カフカ、ニーチェなど。
受取状況を読み込めませんでした