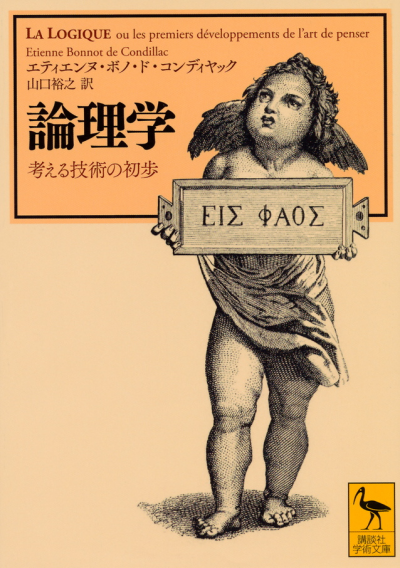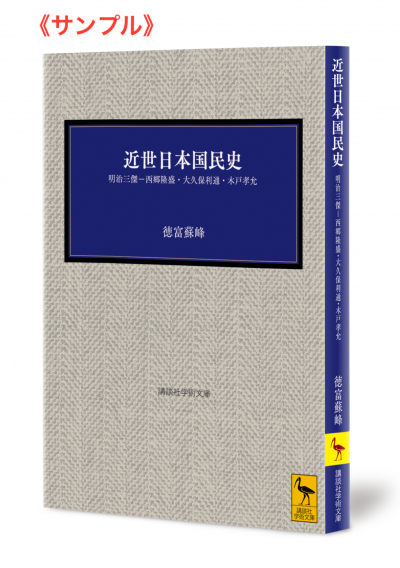論理学 考える技術の初歩
論理学 考える技術の初歩
◆重要◆
【表紙のデザインについて】
・この本の表紙は、
商品画像2枚目にあるサンプルと同様の
統一フォーマットになります。
【内容紹介】
「啓蒙」の18世紀フランスを代表する思想家が最晩年に残した著作、ついに本邦初訳! イギリスから経験論を導入し、感覚や記号に関する独自の体系を作り上げたコンディヤックが若者たちのために書いた教科書。本書は誰にとっても生きる上で役に立つ「正しく考える方法」を習得するための最良の書である。この本で学べば、「諸学問について適切に論じている本を、遅くはないスピードで読み進めることができる」ようになる!
本書は、18世紀フランスを代表する思想家エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック(1714-80年)が最晩年に執筆した書物、待望の本邦初訳である。ヴォルテール、ルソー、ディドロ、ダランベールなど、綺羅星のごとき思想家たちが並び立つ「啓蒙の世紀」のフランスで、彼らと交流をもちながら活動したコンディヤックは、現代の枠組みを用意した立役者の一人だった。にもかかわらず、邦訳の少なさのため、日本ではよく知られることのないまま今日に至っている。みずから影響を受けたデカルト哲学の限界を見極めたコンディヤックは、ジョン・ロック(1632-1704年)やアイザック・ニュートン(1642-1727年)といったイギリスの「経験論」と呼ばれる潮流を積極的に導入し、感覚や記号に関する独自の思想を作り上げた。それは近代科学の成立に少なからぬ寄与をしたことが知られている。
本書は、ポーランド国民教育委員会の要請を受け、論理学の初等教科書として執筆されたものだが、その背景にはコンディヤックが磨き上げた思想体系がはっきり見て取られる。本書は後世にも多大な影響を与え、例えば「近代化学の父」と言われるアントワーヌ・ラヴワジエ(1743-94年)が1789年に出版した『化学原論』は、明らかにこの『論理学』に依拠して書かれている。本書がていねいに解説する「論理学」は、専門家にしか理解できない難解さとはいっさい無縁である。その目的は実に明快で、「正しく考える方法」を身につけることにほかならない。その方法を習得できたなら、コンディヤック自身が言っているように、「諸学問について適切に論じている本を、遅くはないスピードで読み進めることができる」ようになる。それは誰にとっても生きていく上で何より役に立つだろう。ヨーロッパが生み出した本物の技術が、ここにある。
【目次】
この本の目的
第一部 自然はいかにして我々に分析を教えるか。また、この分析という方法に即して観念と心の諸機能の起源と発生を説明すると、どのようになるか
第一章 自然はいかにして考える技術の最初のレッスンを我々に与えるか
第二章 知識を獲得する唯一の方法は分析である。いかにして我々は分析という方法を自然そのものから学ぶか
第三章 分析は精神を正確なものにする
第四章 いかにして自然は我々に感覚的対象を観察させ、さまざまな種類の観念を獲得させるか
第五章 感官で捉えられないものごとについての観念
第六章 同じ主題のつづき
第七章 心の諸機能の分析
第八章 同じ主題のつづき
第九章 感覚能力と記憶力の原因について
第二部 分析の手段と効果についての考察、すなわち、よくできた言語に還元された推論の技術
第一章 我々が自然から学んだ知識はいかにしてすべてが完全に結びついた体系をなすか。自然の教えを忘れたとき、我々はいかにして道に迷うか
第二章 いかにして行動の言語が思考を分析するか
第三章 いかにして言語は分析的方法となるか。この方法の不完全性
第四章 言語の影響について
第五章 抽象的で一般的な観念についての考察。推論の技術はいかにしてよくできた言語に還元されるか
第六章 言語の乱用を改善するための唯一の手段は定義だと考える人がどれほど間違っているか
第七章 言語が単純であれば、推論はどれほど単純になるか
第八章 推論の技巧は何に存するか
第九章 確かさのさまざまな段階。明証性、推測、類推について
解 説
■
著者
エティエンヌ.ボノ.ド・コンディヤック
1714-80年。フランスの哲学者。啓蒙思想家と交流をもちつつ、ロックやニュートンなどのイギリス経験論をフランスに輸入・発展させた。代表作は、本書のほか、『人間認識起源論』(1746年)、『感覚論』(1754年)。
訳者
山口 裕之(やまぐち・ひろゆき)
1970年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。現在、徳島大学准教授。専門は、フランス近代哲学・科学哲学。主な著書に、『コンディヤックの思想』、『人間科学の哲学』、『認知哲学』、『ひとは生命をどのように理解してきたか』ほか。
受取状況を読み込めませんでした