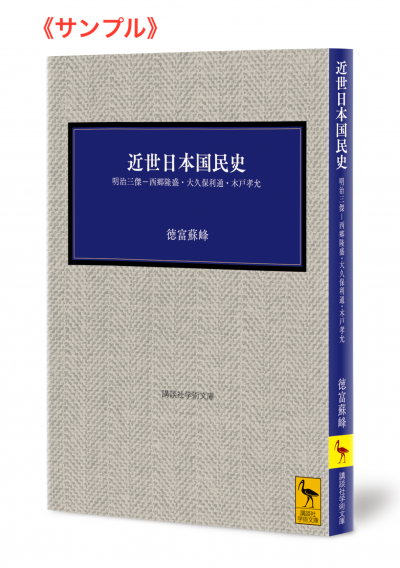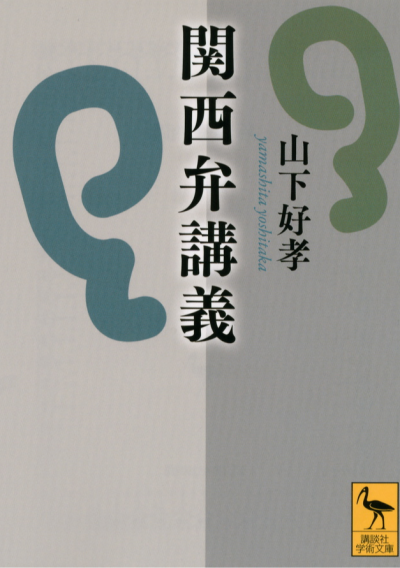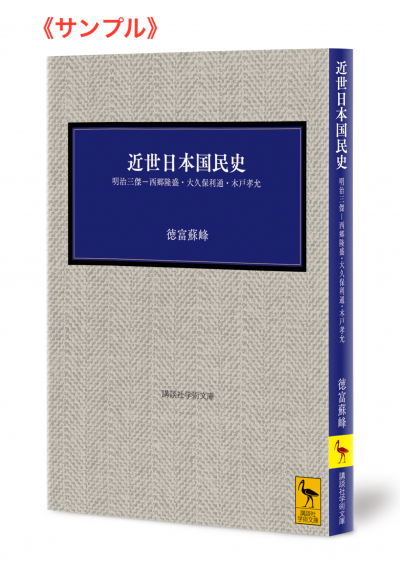関西弁講義
関西弁講義
◆重要◆
【表紙のデザインについて】
・この本の表紙は、
商品画像2枚目にあるサンプルと同様の
統一フォーマットになります。
【内容紹介】
関西人はなぜ声が大きいのか? 声が大きいのではなく声が高いのだ。二千万話者を擁する関西弁は発音の高低を駆使してこそ成り立つ言語なのだ——。強弱アクセントではなく高低のアクセントを導入することでその発音法則を見出し、文法構造によるイントネーションの変化など、標準語とは異なる関西弁独自の体系を解明する。読んで話せる関西弁教科書。めっちゃ科学的。
*本書の原本は、2004年に小社より刊行された。
【目次】
【第一講】関西弁との出会い
【第二講】二〇〇〇万人の関西弁
1 「言語」か「方言」か/2 二一世紀の関西弁へ
【第三講】関西弁の音声学
1 五十音を学ぶ/2 複雑なアクセントを楽しむ/3 動詞の発音にしたしむ/4 イントネーションを感じる
【第四講】関西弁の統語論
1 助詞—関西弁独特の法則/2 否定形—歴史が生んだ多様性/3 可能形—細分化する表現/4 条件表現—「れば」への違和感/5 使役形省略を好む風土/5 使役系/6 敬語—京都・大阪対神戸/7 命令形—やわらかい表現・強い表現
【第五講】関西弁のボキャブラリー
1 ようわかっとんか、自分/2 あ、そうなんや/3 鈴木さん、鈴木はん/4 飴ちゃん/5 大阪で生まれた女やさかい/6 一回生/7 お腹が減った/8 今日の仕事はえらかった/9 まる、ぺけ問題/10 ごもく、ぶたまん、シャベル
【第六講】関西弁の歴史
1 日本とと関西弁の歴史/2 有史以前—東と西/3 奈良時代—「あづまの国」と中央/4 平安時代—漢音が与えた衝撃/5 鎌倉時代—権力と言葉/6 室町、安土桃山時代—「関西弁らしさ」の獲得/7 江戸時代—逆転した力関係/8 明治以降—標準語の制定
【第七講】いくつもの日本語
参考文献/あとがき/文庫版あとがき
■
著者
山下 好孝(やました・よしたか)
1956年、京都市伏見区生まれ。神戸市外国語大学大学院外国語学研究科(イスパニア語学)修士課程修了。北海道大学留学生センター教授。専門はスペイン語学、関西弁学、日本語学、日本語教育。共著に『日本語初歩練習帳』(凡人社)、『「読み」への挑戦』(くろしお出版)、『朝日新聞で日本を読む——中・上級日本語読解教材』(くろしお出版)、単著に『先生と学ぶスペイン語』(同学社)などがある。
受取状況を読み込めませんでした